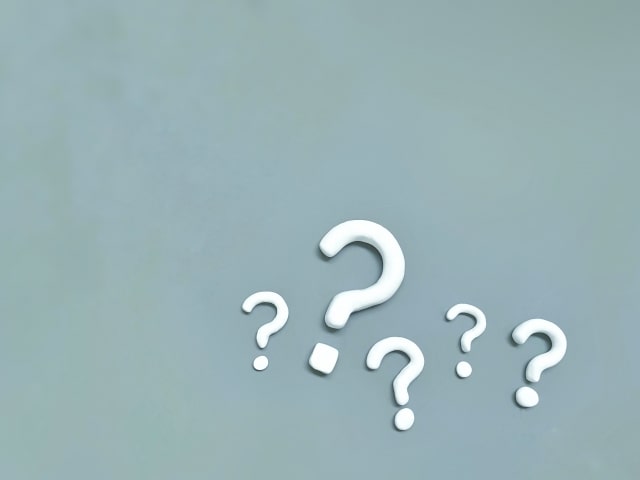3歳未満とは、0歳、1歳、2歳を指します。
- 「未満」は、その数を含まないので、3歳の子どもは3歳未満に含まれません
- 「以下」は、その数を含むので、3歳の子どもは3歳以下に含まれます
幼い子ども向けのサービスで見かける「3歳未満は無料」という表記。
3歳の子どもがいると、我が子は含まれるのかわからなくなることがあると思います。
この記事では「未満」と「以下」の表現の違い、また、飛行機や新幹線の料金についてもご紹介します。
「3歳未満」とは?意味と範囲を確認
まず「3歳未満」という言葉は、文字どおり「3歳に満たない」という意味です。
0歳・1歳・2歳の子どもが該当します。
3歳の子どもは含まれないことになります。
そのため、「3歳未満無料」とあれば、0歳から2歳の子どもはサービスの対象となり、3歳の子どもには料金が発生します。
誕生日で考えると、満3歳になる前日までが「3歳未満」という扱いになります。
例えば、4月10日生まれの子であれば、4月9日までは「3歳未満」、4月10日からは「3歳」となります。
このように、年齢を数えるときは「満年齢」で判断されるのが一般的です。
「未満」とは、「まだその数に達していない」ことを意味します。
つまり、指定された数字未満、すなわちそれより小さい数値を指します。
「未満」という表現は、その年齢を含まないことを覚えておくと理解しやすいでしょう。
「3歳以下」とは?「3歳未満」との違い
「未満」と「以下」はよく混同されがちですが、はっきりとした違いがあります。
「未満」は、指定された数に達していない数値を示し、その数自体は含まれません。
一方、「以下」はその数を含め、それ以下の数値すべてを含むという意味になります。
「以下」という表現は、その数を含む点が「未満」との大きな違いです。
「3歳以下」という言葉は、その年齢を含むという意味になります。
つまり「0歳~3歳」までが「3歳以下」にあたります。
例えば、「3歳以下は無料」と書かれていれば、3歳のお子さんも対象に含まれます。
0歳から3歳の子ども全員が含まれるということになります。
しかし「3歳未満は無料」と書かれていれば、対象は0~2歳までということになります。
この違いは利用料金やサービス内容に直結するため、表示の言葉に注意して確認する必要があります。
続いて、レジャー施設や交通機関などでの3歳未満、3歳以下について見ていきましょう。
レジャー施設での3歳未満や3歳以下の例
ディズニーリゾートの入園料
東京ディズニーランドやディズニーシーでは、3歳以下の子どもは入園料がかかりません。
4歳からチケットが必要になります。
安心してパークを楽しんでいただくために(東京ディズニーリゾート公式サイト)
その他の施設(動物園・映画館など)
動物園や映画館などでも、「3歳以下無料」「3歳未満無料」といった表記を見かけます。
施設によって基準やルールが異なるため、出かける前に確認しておくと安心です。
未満と以下、以上の区別
- 未満:指定された数より小さい(その数を含まない)
- 以下:指定された数を含む、それより下の範囲
- 以上:指定された数を含む、それより上の範囲
未満、以下、以上の違いや使い方はややこしいかもしれませんが、正しく理解しておくことが重要です。
交通機関での3歳未満や3歳以下の例
3歳未満の子どもを連れて飛行機に乗る場合、料金はどうなるの?
国内の飛行機では、生後8日~3歳未満の子どもは「幼児」として扱われることが一般的です(幼児運賃適用)。
座席を利用する場合は子ども料金が必要となりますが、大人一人につき幼児一人を膝上に乗せて同伴することができます。
この場合、追加で座席を購入する必要がなく、運賃もかからないのが通常です。
LCC(格安航空会社)では航空会社ごとに規定が異なるため、利用する際は事前に確認するのが良いでしょう。
以下に3つのパターンでの例を挙げますね。
2歳の子どもが飛行機に乗る場合
例えば、2歳の子どもが飛行機に乗るケースを見てみましょう。
- 大人の膝上に乗る場合の運賃は無料
- 自分の座席が必要な場合は有料(幼児運賃適用)
3歳の子どもが飛行機に乗る場合
続いて、3歳の子どもが飛行機に乗るケースを見てみましょう。
3歳の子どもは「小児」として扱われ、自分専用の座席が必要になります。
この場合、小児運賃が適用されます。
LCCの場合
ローコストキャリア(LCC)として知られるピーチ、ジェットスター、バニラエア、春秋航空などでは、料金体系が異なり、2歳から座席が必要になります。
LCCでは、幼児や小児向けの特別運賃は設定されておらず、大人と同じ料金が適用されますので注意してくださいね。
また、赤ちゃんを膝上に乗せて飛行機に乗る場合も追加料金が発生するので、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
新幹線で3歳未満の子どもの運賃は無料?
新幹線で3歳未満の子どもの運賃は無料です。
ただし、一人で指定席に座る場合は子ども料金が必要です(自由席や、膝の上に座る場合は無料です)。
例外もありますが、基本的な運賃・料金の考え方をまとめると以下のようになります(JR東日本の例)。
- おとな料金:中学生以上
- こども料金(おとなの半額):小学生
- 無料(「おとな」や「こども」1人につき乳幼児2人まで):小学校入学前の乳幼児 ※無料となるのは、膝の上に座る場合と、自由席に座る場合です
JR東日本では、小学校入学前の子どもは、基本的には「おとな」や「こども」一人につき2人まで無料で同乗できることになっています。
(小学校入学前なので、6歳でもまだ幼稚園に通っている場合は無料ということになります)
ただし、小学校入学前の子が指定席に一人で座る場合は、特急券と乗車券が必要です。
以上のように、新幹線の料金は3歳が区切りではないのですが、この記事では2歳や3歳のお子さんが含まれるかどうかについて主に取り上げているので、以下に2つのパターンでの例を挙げますね。
3歳の子どもが新幹線に乗る場合
例として、3歳以下の子どもが新幹線に乗る場合を見てみましょう。
先ほどお伝えしたように、小学校入学前の子どもは、基本的には「おとな」や「こども」一人につき2人まで無料で同乗できます。
- 膝の上に3歳児を座せる場合の運賃は無料
- 3歳児が一人で座席を使う場合、自由席なら無料
- 3歳児が一人で座席を使う場合、指定席ならこども料金の指定席特急券と乗車券が必要です
6歳の子どもが新幹線に乗る場合
続いて、6歳の子どもが新幹線に乗る場合を見てみましょう。
- 6歳で幼稚園生の場合は、3歳の子供の例と同じです
- 6歳で小学生の場合:こども料金の特急券と乗車券が必要になります
グリーン車やグランクラス、寝台券、乗車整理券は、こども料金の設定がないため、子供も大人と同じ料金が必要となります。
日常生活での「3歳未満」「3歳以下」
交通機関やレジャー施設だけでなく、日常生活のさまざまな場面でも「3歳未満」「3歳以下」という表現が使われます。
例えば、保育園の入園条件や習いごとの募集条件に「3歳未満」といった表記があることがあります。
また、地域のイベントや親子向け教室でも年齢制限が設けられる場合があります。
こうした場面でも「未満」と「以下」の違いが影響するため、見慣れた言葉でも意味を正しく理解しておくことが役立ちます。
英語や記号での「3歳未満」「3歳以下」
英語での表現
- 3歳未満 … under 3 years old 3歳になる誕生日を迎える前までの子どもを指します。例えば2歳のお子さんは含まれますが、3歳になった瞬間からは含まれません。海外の文書や統計データでもよく使われる表現です。
- 3歳以下 … up to 3 years old 3歳のお子さんも含む範囲で、保育園や施設の案内などで見かけることがあります。0歳から3歳までのお子さん全員が対象になります。
数字・記号での表現
- 3歳未満 … age < 3 このように記号で表すと、3歳未満が0〜2歳であることがひと目でわかります。
- 3歳以下 … age ≤ 3 3歳を含む範囲を示すときに使います。
文章や案内文、契約書、国際的な情報に触れるときも、どの年齢が対象か直感的に判断できます。
よくある疑問と勘違い
- 3歳未満には3歳も含まれるの? → 含まれません。3歳の誕生日を迎えた時点で「3歳未満」ではなくなります。
- 誕生日当日はどう数える? → 誕生日を迎えた瞬間から「満3歳」となります。誕生日当日はすでに「3歳未満」には当たりません。
- 「未就学児」と「3歳以下」は同じ意味? → 違います。「未就学児」は小学校に入る前の子ども全体を指しますが、「3歳以下」は3歳までの年齢に限定されます。
- 案内文で誤表記がある場合 → 「3歳未満(3歳を含む)」のように矛盾した書き方に出会うこともあります。実際に利用する際はスタッフに確認しましょう。
このように、似た表現でも対象となる年齢が異なるため、言葉の使い方に注意しましょう。
「数え年」は気にしなくてOK
ちなみに、年齢の数え方には「満年齢」と「数え年」があります。
現在は多くの制度や施設で「満年齢」が使われています。
「満年齢」は誕生日を迎えた時点で1歳加算される方法で、これが一般的な年齢表記です。
一方で「数え年」は、生まれたときを1歳とし、元日を迎えるごとに1歳加算される方法です。
昔は広く使われていましたが、現在は日常生活ではあまり用いられません。
「3歳未満」「3歳以下」の基準になるのは「満年齢」なので、数え年について気にしなくて大丈夫です。
未満・以下・以上・超過 基本の表現を整理
- 未満 … その数を「含まない」下の範囲。例:3歳未満=0歳・1歳・2歳。
- 以下 … その数を「含む」下の範囲。例:3歳以下=0歳・1歳・2歳・3歳。
- 以上 … その数を「含む」上の範囲。例:3歳以上=3歳・4歳~。
- 超える/超過 … その数を「含まない」上の範囲。例:3歳超=4歳~。
この基本を理解しておけば、どの年齢までが対象なのかを迷わず判断できます。
まとめ
この記事では「未満」「以下」「以上」の違いに触れました。
- 「3歳未満」=0~2歳(誕生日の前日まで)
- 「3歳以下」=0~3歳(3歳を含む)
- 交通機関やレジャー施設、日常の場面で料金や条件に影響することがある
「未満」と「以下」は似ているようで大きな違いがあります。
- 未満:指定された数より小さい(その数を含まない)
- 以下:指定された数を含む、それより下の範囲
- 以上:指定された数を含む、それより上の範囲
お出かけや手続きをするときには、この違いを理解しておくと安心です。